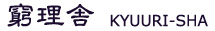第28号が発売されました!
本日は創刊10周年記念の『窮理』第28号の発行日です。
いつものように以下に各記事の概要を案内いたします。
物理学者とエッセイの系譜/永田和宏
歌人で生命科学者の永田和宏先生には、日本の物理学者が残してきたエッセイの伝統を俯瞰していただきました。寺田寅彦や中谷宇吉郎らの作品を例に、面白がる精神で日常を探究する、研究者に不可欠な気質を指摘されています。現代の担い手として、第2号でご執筆いただいた橋本幸士先生も登場します。
発見と驚きと感動の記述/蜂飼 耳
詩人の蜂飼耳先生には、詩と科学の交差する領域について貴重なエッセイをご寄稿いただきました。
一見遠く離れた関係にみえる詩と科学が、実は発見や驚き、感動という人間の根源的な営みを共有しており、そこには詩の本質や言語の冒険性や人間存在への問いも背景にあることを示唆する啓発的論考です。
サイエンスエンターテイナーという職業 二人の先人に想いを馳せて/五十嵐美樹
当ホームページで以前に紹介したことがある五十嵐美樹先生には、サイエンスエンターテイナーという職業について、特にショーの背景で工夫されている事や、ご自身の活動の源であるあの偉人の母国へと訪問した体験記も交えながら、職業と趣味、プロとアマの境界などにも触れていただきました。
ファラデーに学ぶこと/市村禎二郎
かつて英国王立研究所で客員研究員をしていた市村禎二郎先生には、歴代所長の代表ともいえるマイケル・ファラデーの生涯と業績を紹介いただきました。
科学的貢献だけでなく、人間性や教育への情熱にも触れており、現代に通じる学びの姿勢が伝わってきます。
詳しい注や補足なども充実した小伝エッセイです。
寺田寅彦「随筆難」と父/花輪昭太郎
精神科医の花輪昭太郎先生には、ご尊父と寺田寅彦「随筆難」をめぐる背景をご執筆いただきました。
誤解が随筆の種となる…
ならば、誤解は理解のための大事な摩擦と言えるのではないか?
SNSなら炎上するようなネタも書き手によっては上質な随筆になる、その違いこそ「文」のなせる「芸」なのでしょう。
演劇「光子の裁判」/渡辺美帆子
劇作家の渡辺美帆子さんには、朝永振一郎の傑作裁判劇「光子の裁判」を舞台化し、上演した記録について紹介していただきました。
難解な量子力学の概念を、台詞や演出をいかに工夫して観客に体感させるか、さらに俳優の役割や表現を通して、科学と演劇の境界に挑む舞台を疑似体験してみてください。
学術誌ヒストリー(四)初期の『Phiosophical Transactions』を再読する/柴田和宏
4回目となる連載「学術誌ヒストリー」は、17世紀に創刊された世界最初期の学術雑誌『Philosophical Transactions』について柴田和宏先生に紹介いただきました。
当時は現代のような査読つき論文発表の場ではなく、情報の報知・交換が主であったことがフォーカスされます。その伝統の受容にも注目です。
音楽談話室(二十八)AIは人間並みの芸術作品が作れるか?/井元信之
井元信之先生の連載「音楽談話室」は、前回に続くAIと芸術作品について。
今回は、戦争で疲弊した祖国をショパンが想って作った歌曲を取りあげ、AIが模倣できない表現の深層に迫ります。
芸術の本質を問う根源的なテーマであり、検閲と未発表作品と創造の関係についても考えさせられる内容です。
仁科芳雄をめぐる旅(二)岡山市(後編)第六高等学校/伊藤憲二
伊藤憲二先生の仁科芳雄連載は、前回に続く岡山市をめぐる後編で、今回は第六高等学校時代。
入学する年に肋膜炎になってしまい休学も多かった仁科先生に、進学の相談など親身にのってくれた恩師・松尾哲太郎が登場します。
温情に溢れていた松尾先生は、後の仁科芳雄のロールモデルかもしれません…
科学随筆UN PASSAGE(一)雲とかなしみ/西一六八
今回から始まった新企画「科学随筆UN PASSAGE」の初回は、話題の『随風01』でも知られる西一六八さんの貴重なショート科学エッセイ。
落ち込んだ時ほど人の感情に影響を与えるものって何でしょう…
西さんの自然界への気づきと発見が、叙情味ゆたかに綴られるアイスクリーム文学と言ってもよい秀作。
科学随筆U30(四)茶碗の輝き/藤むすめ(講評:佐藤文隆、細川光洋)
今回で4回目となった「科学随筆U30」は、寺田寅彦推しの藤むすめさんの『柿の種』を思わせる詩的な科学随筆。
宋代から伝わる、世界に3碗しかない曜変天目茶碗をめぐる研究で見出された美しさの秘密とは何か…
科学と芸術が交差する世界、そして研究者を魅了する「輝き」を味わってみてください。
窮理のことのは(二)全体は部分の総和たり得るか/今野真二
今野真二先生の連載「窮理のことのは」では、九鬼周造の哲学を通じて、言語における「全体は部分の総和」というテーマを考え、抽象性の観点から検討します。
こうした話題は、AI研究にも関わるもので、例えば九鬼の『偶然性の問題』での因果系列の話は、AIと因果推論の問題に広げたら面白そうです。
窮理逍遙(二十一)才気あふれるリンデ/佐藤文隆
ご逝去された佐藤文隆先生の連載「窮理逍遙」。最後となってしまった回は、宇宙物理学者アンドレイ・リンデの追想記です。リンデ先生も佐藤先生の訃報を知ったら驚かれるはずです。
名だたる世界中の物理学者との思い出を綴る本連載は佐藤先生の人としての親交の深さを物語るものでした。
黙祷
窮理の種(二十七)ラジオ百年/川島禎子
川島禎子先生の連載「窮理の種」は、寺田寅彦のラジオに関する連句(発句と脇)と周辺の話について紹介いただきました。
今年はラジオ放送100周年。初放送は1925年3月22日9:30の発信。耳の敏感な寅彦先生には、放送当初のラジオの音はどんな印象だったでしょう。いわんや、100年後の現代のラジオをや…