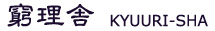聴き比べ:古典音律(ピタゴラス音律、純正律、中全音律、ウェル・テンペラメント)と平均律
そもそも、なぜ古典音律を話題にするのかですが、まずはこれを聴いてください。視聴にあたってはステレオフォンまたはステレオヘッドフォンを使用されることをお薦めします。
Why am I talking about the classical tunings and temperaments, in the first place?
Please listen to Sound Source 1. (Stereo earphones and headphones are recommended.)
音源1:終止形(平均律)
Sound Source 1: British National Anthem (the first half) by Equal temperament
ま、曲の終わりによくありそうな、終止形の和音です。我々に馴染み深い「平均律」で弾きました。これを、純正律と聴き比べましょう。平均律、純正律、平均律、純正律の順で弾きます。
I played this in the “Equal temperament,” which is familiar to you and me. Let’s compare this with the Just intonation. I will play it, for comparison, in the following order: Equal temperament, Just intonation, Equal temperament, and Just intonation.
音源2:終止形を平均律、純正律、平均律、純正律で演奏
Sound Source 2: of British National Anthem by Equal temperament, Just intonation, Equal temperament, and Just intonation.
いかがでしょう? 純正律はピュアな感じで、平均律は、なんか人混みの中みたいにザワザワ、モヤモヤしていませんか? 楽器店に行って電子楽器でこれをやると、お店のスタッフさん達は、「平均律ってこんなに濁ってたんですか?純正律の方がずっと澄み切った響きですね」と、ビックリします。
それなら、なぜみんな純正律を使わず、世の中平均律ばかりになっているのだ? と思いませんか? そう、鍵盤楽器の調律法は、ピタゴラス音律、純正律、中全音律、ウェル・テンペラメントを経て、最後に平均律になって、以後現代まで200年近くずっと平均律です。今聴いていただいた通り、平均律はそんなに美しい響きじゃないのに。
何でそんなことになったのか、順を追ってお話ししましょう。まず、西洋音楽の和音は最初からドミソだったのではなく、初めはドとソだけだったんですね。ちょっと弾いて見ましょう。
How do you like it? Doesn’t the Just intonation sound much purer, and the Equal temperament sound zany and fuzzy (like you listen to it in a crowd)? When I demonstrate this at music shops, the staffs always say, “I didn’t know that the Equal temperament is so muddy. The Just intonation is much clearer.”
If that’s the case, then why is it the case that no one is using Just intonation and all we have is the Equal temperament? Yes, the tuning method for keyboard instruments has started with Pythagorean tuning, and then Just intonation, Mean-tone temperament, Well temperament, and finally, Equal temperament. The Equal temperament has been dominating for nearly 200 years since then until the present day, although, as you have just heard, the mean rule does not sound so beautiful.
Let me tell you in order how this situation came to be. First of all, chords in Western music were not always do-mi-so from the beginning, but in the beginning, they were only do and so. Let’s play this and see the difference.
音源3:ドミソ和音とドソ和音を純正律で演奏
Sound Source 3: do-mi-so and do-mo chords in Just intonation
ドソの和音は真ん中のミが無いので、中抜けして虚ろな感じがします。このドとソが1番よくハモるのは、周波数の比が2:3つまり1.5倍になっているときです。この2:3という周波数比を重ねてドソレラミシ・・・と延長して出来た音階をピタゴラス音律と言います。最初にお聞きいただいた純正律より前に成立した調律法です。ちょっと弾いてみましょう。
The do-so chord doesn’t have mi in the middle, so it sounds hollow and empty. The do-so chord harmonizes best when the frequency ratio is 2:3 (= 1.5). If we make a scale piling up this 2:3 frequency ratio and extending it to do-so-le-ra-mi-si… is called the Pythagorean scale. This tuning method was established prior to the Just intonation you heard in the beginning of this article. Let’s listen to it a little more.
音源4:ドソレラミシをピタゴラス音律で演奏
Sound Source 4: Playing do-so-le-la-mi-si in Pythagorean tuning
これはド・ソとかレ・ラのような五度音程の和音しか使わない音楽にピッタリの音律ですが、今やそのような大昔の音楽は流行らなくなったので、聞いても「ああ、あれか」という曲はありません。しかし近代現代の音楽には大昔のエキゾチックな効果を狙って、五度だけの和音が使われたりします。例を二つ挙げましょう。1つ目はドビュッシーのピアノソロ用の前奏曲集第1巻から第10曲「沈める聖堂」です。(日本語で「沈める寺」と呼ばれていますが、5世紀フランスのイスという伝説都市の寺院のお話なので、ここでは聖堂と呼ぶことにします。)
It is not easy to find poplar music pieces that use the fifth chords only. In modern music, however, the fifth chords are sometimes used for exotic effects. I will give two examples. The first one is Debussy’s “The Sunken Cathedral.”
音源5:沈める聖堂の冒頭をピタゴラス音律で演奏
Sound Source 5: The beginning of the Sinking Cathedral in Pythagorean tuning
2つ目はレスピーギの管弦楽曲「ローマの松」から「カタコンベ付近の松」の部分です。
The second is the passage “Pines near the Catacombs” from Respighi’s symphonic poem “Pines of Rome.”
音源6:「カタコンベ付近の松」から部分的にピタゴラス音律で演奏
Sound Source 6: “Pines near the Catacombs” played in Pythagorean tuning
ちょっとお寺のお坊さん達のお経みたいですね。音源4~6は五度音程しか鳴らしていませんので、ピタゴラス音律のありがたみが目が覚めるほどにはわかりませんが、それでもピタゴラス音律にこだわるギリシアから古代の西洋人は繊細だったんですね。でも徐々に三度音程(ドミの和音)が好まれて来るようになると、ピタゴラス音律では対応できない事態が目立って来ます。
そう、ピタゴラス音律は次第に純正律に取って代わられます。なぜそうなったか? ピタゴラス音律には欠点が二つあります。1つ目はウルフの存在です。ウルフ? それは次のようなものです。
ピタゴラス音律の考え方に従って周波数比1.5の音程でドソレラミシファ#ド#ソ#ミ♭シ♭ファ→ドと五度で音階を作ると、きちんとドには戻らないのです。これは1.5倍という周波数比を何回掛けても2の冪数にならないためです。それでもドをドに戻さないわけには行かないので、どこかに1ヶ所、1.5倍よりもかなり狭い音程を作らなければなりません。普通は、ソ#とミ♭のところに作ります。こんな和音です。
It sounds like the chanting of monks at a temple. I agree that it is not easy to differentiate the pureness of fifth chords in Equal temperament from that of the Pythagorean tuning. So, as people gradually tend to love do-mi-so chords over do-so chords, the Pythagorean tuning gradually gives the way to the Just intonation.
Let’s see the situations when Pythagorean tuning had to give the way to Just intonation. Actually, Pythagorean tuning has two drawbacks, the first of which is the existence of Wolf. Wolf? What is it?
If you try to tune the twelve tones by the Pythagorean tuning by making a scale with a frequency ratio of 1.5, like Do-So-Re-La-Mi-Si-Fa#-Do#-So#-Mi♭-Si♭-Fa-Do, you will not get back to the proper Do. This is because no matter how many times you multiply the frequency ratio 1.5, it will never reach a power number of 2 (= 2^n = n octave difference). But we anyhow need to return to the initial “do.” This means that we have to set an abnormal fifth somewhere that is much narrower than the purely harmonized fifth. Usually, we create it at the fifth between the so# and the mi♭. This is called the “Wolf” in Pythagorean tuning.
音源7:ピタゴラス音律でソ#ミ♭の和音を演奏
Source 7: Playing a Wolf: So # and Mi Flat chord in Pythagorean tuning
どうです? 酷いでしょう? とても音楽に使えません。これをウルフと言います。狼の鳴き声のように非音楽的な和音という意味です。この「五度を積み重ねてもドがドに戻らない矛盾」を一手に引き受ける、ウルフというかわいそうな和音は、あとで純正律や中全音律にも出て来ますので、名前を覚えておいてください。ウルフです。
さてピタゴラス音律の2つ目の欠点ですが、実はこの2つ目の欠点を無くすために考えられたのが純正律なんですが、その欠点とは、ピタゴラス音律ではドとミが綺麗にハモらないのです。
What do you think? It’s terrible, isn’t it? You can’t use this chord for your composition or arrangement. The meaning of wolf is a non-musical chord like a wolf’s cry. Please remember the name of this poor chord, Wolf, because it will appear later in the just intonation and the mean-tone temperament as well.
Now, the second drawback of the Pythagorean tuning, which was actually conceived to eliminate, is that, in the Pythagorean tuning, “do” and “mi” don’t harmonize nicely.
音源8:ピタゴラス音律でドミ和音を弾く
Sound Source 8: Playing a do-mi chord in the Pythagorean tuning
そんなに酷い和音ですか? とおっしゃるかもしれませんが、実際の曲で比較した方がわかりやすいと思いますので、たとえばキリスト教で歌われる「神ともにいまして」という歌があります。これを純正律で、続けてピタゴラス音律で弾いてみます。
Maybe you didn’t feel so strange at this do-mi chord. But that is because a chord containing only “do” and “mi” is too simple. If you hear real music with full of do-mi-so, fa-ra-do, and so-si-re, then you will notice the big difference. Next example is a hymn “God be with you. I will play it in the just intonation, followed by the Pythagorean tuning.
音源9:「神ともにいまして」を純正律とピタゴラス音律で演奏
Sound Source 9: “God be with you” played with the Just intonation and the Pythagorean tuning.
倍音の少ないピアノの音色で演奏しても、差がはっきりわかりますね。
では純正律には欠点はないのでしょうか? あります。先ほども言いましたが純正律にもウルフがあるのです。しかもウルフの位置を変えられるピタゴラス音律と違って、純正律のウルフは理論上レとラから成る和音に生じて、これは動かせません。弾いてみましょう。
You can clearly see the difference even when played on a piano tone, which has few overtones.
So, is there any flaw in the just intonation? Yes, there are. As I mentioned before, the just intonation also has a wolf (actually, wolves, if you want to play with many # or flats). And unlike the Pythagorean tuning, where the position of the wolf can be changed, the wolf in the just intonation is theoretically fixed on chords consisting of the “re” and “la,” and this wolf cannot be moved. Let’s play it.
音源10:純正律でレラ和音を演奏
Source 10: Playing a Wolf: re-la chord in the just intonation.
うゎ酷いですね。このレとラの和音はハ長調にもヘ長調にもたくさん出て来ますし、何と言ってもニ長調やニ短調の主和音です。これではモーツァルトが満足できる筈はありません。
そこで登場したのが中全音律です。ミーントーンという英語も日本語としてよく使われます。その仕組みは本誌第21~23号を読んでいただくとして、モーツァルトの好きなニ長調とニ短調の曲を純正律で弾くとどうなるか、やってみましょう。最初はピアノソナタ(ケッヘル番号576)の第3楽章の最初の方の一節です。
Wow, that’s terrible. The re-la chord is frequently found in C major and F major, and is even the main chord of D major and D minor. Mozart would never have been satisfied with this.
This is where the mean-tone temperament came in. The English word “mean-tone” is also often used as a Japanese word. For the details of how it works, please refer to No. 21-23 of “Kyuuri”. Let’s see what happens when we play Mozart’s favorite pieces in D major and D minor using the just intonation. The first is a passage from the beginning of the third movement of the piano sonata (Köchel number 576).
音源11:純正律と中全音律でK.576のソナタ第3楽章の一節を聴き比べ
Sound Source 11: Compare a passage from the third movement of the Sonata in K.576 in the just intonation and in the mean-tone temperament.
うわ全然違いますね。次は二短調のピアノ協奏曲(ケッヘル番号466)の冒頭です。
Wow, they are totally different. Next is the beginning of the piano concerto in D minor (Köchel number 466).
音源12:純正律と中全音律でK.466の協奏曲冒頭を聴き比べ
Sound Source 12: Comparison of the beginning of the concerto K.466 in just intonation and in mean-tone temperament.
はい、全然違いますね。せっかくピタゴラス音律を純正律に改良したのですが、18世紀後半の作曲家モーツァルトを演奏するためには、それでもダメで、中全音律が必要だったことがわかります。モーツァルトが愛した中全音律というのは、こういうことだったのです。
こうやって中全音律ならモーツァルトの曲は全部美しく弾けますので、モーツァルトだけでリサイタルを開けます。そしてリサイタルの最後にアンコールを弾くことになったとします。ここで、「皆様最後にお別れの曲を弾きます」などと言って19世紀前半の作曲家ショパンの「別れの曲」を弾くと大変なことになる、と本誌に書きました。やってみましょう。
Yes, they are totally different. We went to the trouble of improving the Pythagorean tuning to the just intonation, but that was not enough to play Mozart, a composer of the late 18th century, and we can see that the mean-tone temperament was necessary. This is what Mozart meant by the mean-tone that he loved so much.
In this way, with the mean-tone temperament, all of Mozart’s pieces can be played beautifully, and a recital can be held with Mozart alone. And at the end of the recital, you decide to play an encore. I wrote in “Kyuuri” that it would be a big problem if you played Chopin’s “Farewell”, a composer from the first half of the 19th century, saying, “I will play a farewell piece for the last time, ladies and gentlemen.” Let’s do it.
音源13:モーツァルトのトルコ行進曲の冒頭と最後を中全音律で演奏。続けてショパンの別れの曲の冒頭を演奏
Sound 13: Play the beginning and the end of Mozart’s Turkish March by mean-tone temperament. Continue to play the beginning of Chopin’s “Farewell.”
うゎ、せっかく美しく終わったモーツァルトのリサイタルが台無しですね。同じことは、ベートーヴェン(モーツアルトの晩年に生まれ、ショパンが7才の頃に亡くなった)の曲でアンコールを弾いても起こり得ます。
Wow, you just ruined a beautiful Mozart recital. The same thing happened if you play an encore of a piece by Beethoven.
音源14:ベートーヴェン「悲愴」第2楽章冒頭を中全音律で演奏
Source 14: The beginning of the second movement of Beethoven’s ‘Pathétique’ in Mean-tone temperament.
これも酷いですね。こういうわけで、ベートーヴェンやショパンを自由に弾こうと思ったら、中全音律でもダメなことがわかりました。実はモーツァルトより前のバッハ(モーツァルトが生まれる5年前に亡くなった)のころ、すでに中全音律はありましたが、既にバッハは24長調短調を駆使していたので、中全音律で演奏すると悲劇が起こります。
そこで考案されたのが、ウェル・テンペラメントという音律です。日本語では快適な音律という意味です。これは多種類あります。詳細は本誌をお読みいただくとして、ここではとりあえずウェル・テンペラメントでショパンやベートーヴェンが気持ちよく弾けることだけ確認しておきましょう。数ある中、ヴェルクマイスター第Ⅲ音律とキルンベルガー第Ⅲ音律が有名ですが、ここではバッハの弟子であるキルンベルガーの第Ⅲ音律で弾いてみましょう。
This is also terrible. This tells that if you want to play Beethoven or Chopin freely, even Mean-tone temperament is not good enough.
This is why the Well temperament was invented. There are many different types. For now, let’s just confirm that you can play Chopin and Beethoven comfortably with the Well temperament. Of the many, the Werckmeister III temperament and the Kirnberger III temperament are the most famous, but let’s play here in the Kirnberger III temperament, a pupil of Bach.
音源15:キルンベルガー第Ⅲで別れの曲冒頭と悲愴第2楽章冒頭を演奏
Tone 15: Play the beginning of the Farewell and the beginning of the second movement of the Pathetique in Kirnberger III.
はい、大丈夫ですね。こうしてウェル・テンペラメントによって、どんな調のどんな和音でも一応不都合なく弾くことができるようになりました。
実際、ヴェルクマイスター第Ⅲ音律とキルンベルガー第Ⅲ音律と平均律の違いは、とても微妙です。調律をするのであれば、違いがわかる和音ばかり選んで鳴らしますのでわかりますが、曲を聞いただけで聴き分けるのはそう簡単ではありません。それにもかかわらず、「平均律だけで用を済ませ、他は忘れてしまっていいのだろうか?」と、私は考えます。それについてはまた別途ということで、今日はここまでにします。ではまた。
Yes, it’s all right. Thus, by means of the Well temperament, you can now play any chord in any key without any inconvenience.
In fact, the difference between the Werckmeister III temperament, the Kirnberger III temperament and Equal temperament is very subtle. Nevertheless, I wonder, “Can we just do the Equal temperament and forget about the rest?” I think. I’ll talk about that another time, so that’s all for today. See you next time.