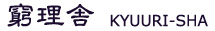本日は『窮理』第27号の発行日ということで、いつものように以下に各記事の概要を案内いたします。
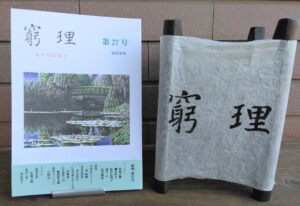
オッペンハイマーの謝罪と回想/山崎正勝
映画『オッペンハイマー』を観た方は多少なりともオッペンハイマーという物理学者の量子的ともいえる複雑な人物像を垣間見たかと思います。が、本稿では映画では取り上げられていない幾つかの事実を通して、後世の科学者が何を学ぶべきかについて問題提起しています。原爆開発へと進んだ動機、矛盾した行動、広島・長崎への原爆投下後の謝罪と不可思議なその後の政治的執着など、戦後、平和運動へと向かったアインシュタインやラッセルとは異なった行動をとったオッペンハイマーには何が足りなかったのか、幾つかの角度からフォーカスしていきます。
なお、本稿の参考記事として第22号で取り上げた小沼通二「朝永振一郎・ゲーテ・「科学にひそむ原罪」」および政池明「ハイゼンベルクの核開発」も挙げておきます(→)。
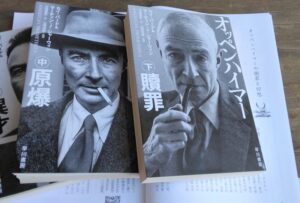
人工知能狂想曲/細谷晴夫
画像生成や翻訳などの言語学習をはじめとする近年の人工知能(AI)研究の驚異的な進展には目を瞠るものがあります。「脳を創る」ことを目標にしてきた計算神経科学は、深層学習や強化学習を通して全脳を模倣した人工知能研究へと現在も進んでいます。“人間並み”へと突き進むAIの進歩を前に、本稿では最前線の研究に取り組む当事者の“人間”としての複雑な胸中が吐露されています。
参考記事として、第17号の甘利俊一先生よる巻頭エッセイ「人工知能と社会」を挙げておきます(→)。
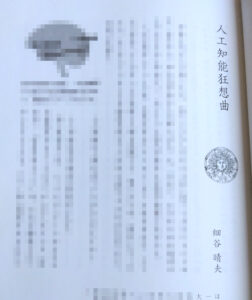
湯川秀樹の歌に学ぶ/松村由利子
巻頭で取り上げたオッペンハイマーは、T.S.エリオットの詩を愛唱し自らも詩を創作しました。科学者と詩歌にはどのような関係性があるでしょう。本稿では、日本初のノーベル物理学賞受賞者でもある湯川秀樹の短歌を通して、科学者が詩歌によって自身の心の中に向かう際に必要とされる感覚や感性について考えていきます。湯川の生い立ちや家庭環境、加速器や原子爆弾を詠んだ歌などをヒントに科学者と詩歌の“遠いようで近い”関係性を探ります。
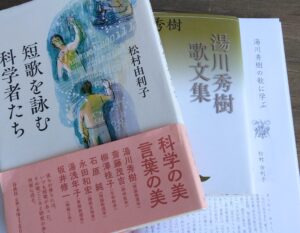
ヒトとイヌの関わり 動物文化史の観点から/溝口 元
地球における人間と犬の長い付き合い。本稿では、動物文化史の観点からヒトとイヌの関わりについて、特に日本での歴史を中心に紹介しています。戦後になってから話題をよんだ出来事として、平成時代に発売されたソニーのイヌ型ロボット「アイボ(AIBO)」があります。生身でないイヌの登場によって現代人の死生観を浮き彫りにした一例と言えます。その後も21世紀に入り、ペットとしてのイヌのクローン化やDNAの保存問題など、生命倫理にもふれる話題を取り上げながら、ヒトとイヌをはじめとする動物との関係についても考えていきます。
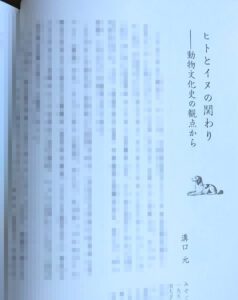
原子論について デモクリトスとハイデガーの観点から/武井徹也
今年は国際量子科学技術年。巻頭で取り上げたオッペンハイマーが米国に初めて導入した量子力学とそれを基礎に製造された原子爆弾。これらは古代ギリシアの哲学者デモクリトスたちが確立した“原子論”の系譜を汲むものです。本稿では、この古代原子論の始まりや成り立ちを通して、ハイデガーの存在論にも踏み込み、「存在する(ある)」ということの哲学的思惟の違いや、デモクリトスたちとハイデガーの関係性を考察します。そこから見えてくる現代における科学と哲学の相関性を、寺田寅彦の『物理学序説』やルクレティウスを足掛かりに見ていきます。
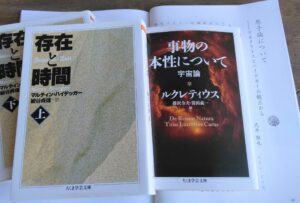
学術誌ヒストリー(三)境界線上の『科学』/秦 皖梅
第3回は日本を代表する歴史ある岩波書店刊行の科学雑誌『科学』について。本稿では、石原純や岡田武松、寺田寅彦らも尽力して創刊された『科学』の意外な特殊性にスポットを当てます。創刊された時代は折しも日本の科学雑誌の出版ブーム。当時の『科学』が目指していた分野をまたいだ交流に見られた一例を紹介しつつ、『科学』がモデルとした『ネーチャー』(Nature)に倣った寄書欄をめぐる変遷も鳥瞰していきます。そこから見えてくる『科学』が目指そうとした大衆と専門の特殊な“境界”が浮かび上がってきます。

音楽談話室(二十七)作品より人生を鑑賞する/井元信之
前回のラフマニノフとスクリャービンの話に続く、芸術作品だけでなく芸術家の生涯も「鑑賞」するという話題について。前回はAIが人間並みに“演奏する”場合でしたが今回は“絵を描く”場合を例に、NHKで特集されたベルトラッキという贋作画家を通して、私たちは何を鑑賞するものなのか、本物と偽物を見分けることが重要なのか、そこから反映されるAIのあり方など、うっかりしていると知らぬ間に流されてしまう現代社会の陥穽をついたAI芸術論を展開しています。
参考記事として本連載第9回と第10回で取り上げた「お宝と贋作①②」も挙げておきます(→)。
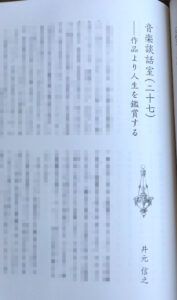
仁科芳雄をめぐる旅(二)岡山市(前編)中学校と烏城/伊藤憲二
第2回は前回までの里庄町から舞台は岡山市へ。前編の今回は旧制岡山中学と中学校のあった岡山城の本丸(通称、烏城)周辺(後楽園など)を多くの写真を眺めながら巡ります。岡山という街が城下町であり、城を中心に重要施設が拡がっていることもよく分かります。旧制岡山中学の後身である岡山朝日高校の歴史資料を通して、仁科の中学時代の交友が後の人生に大きな役割を果たしていたことも窺えます。幼少期の仁科芳雄を育んだ里庄、浜中とは異なる岡山市という環境をしばし旅します。

科学随筆U30(三)技術発展が果たす意外な役割/植田康太郎(講評:佐藤文隆、細川光洋)
U30企画第3回は、物理学の概念を理解する際に技術発展によって誕生した具体例が効果的である、という意外な話が取り上げられます。特に本稿で挙がる具体例には、大きく分けて2つのタイプがあるという点がポイントです。物理概念には目に見えない抽象的なものが多いこと。それゆえに人に分かりやすく伝えることが難しいこと。そこに目をつけた執筆者のエッセイ展開の妙味に要注目です。
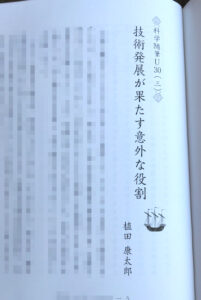
窮理のことのは(一)人・言語・思考 日本における源流を探る/今野真二
今号から始まった新連載の第1回目は、今野先生の研究テーマの肝である「人・言語・思考」について論じていただきました。その際、研究の土台としている「ことがら情報」と「気持ち・感情情報」のモデルに、人間の「思考」をどのように位置づけるかについて手始めに取り上げます。特に、言語学には「抽象的な記号体系」と「具体的な人間の言語表現」の2つの道があることがヒントになります。この2つの道は人文科学と自然科学を示唆するもので、両者を観察・分析・考察するのは他ならぬ“人間”であることに視点が移されていきます。
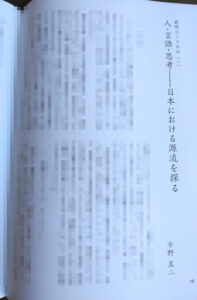
窮理逍遙(二十) むかし気質のエーラース/佐藤文隆
今回は一般相対論の研究で知られるドイツの物理学者ユルゲン・エーラースとの思い出話。エーラースが量子力学の泰斗ヨルダンと出会い、多くの興味深い研究が生まれたこと。そこには一般相対論研究が下火となったり流行したりした一連の時代の流れがあったこと。そして、最終的に日本で初めての一般相対論の国際会議が京都で開催されるまでの背景が語られます。

窮理の種(二十六) 竹隠のひととき/川島禎子
第26回は若かりし20代の寺田寅彦と英国留学から戻ったばかりの夏目漱石をめぐる俳句の背景について。互いにまだ何者でもなかった時代の“先生と生徒”という純粋な関係を想像させるこの俳句には、当時の二人の心中に潜む憂いが見え隠れしています。『吾輩は猫である』を書いた漱石と『団栗』を書いた寅彦。創作前夜の二人の貴重な時間を味わってみてください。